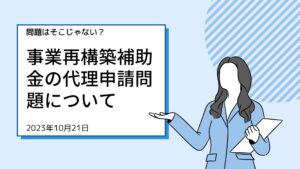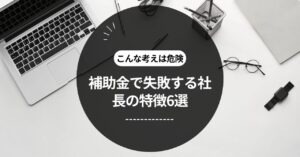補助金交付申請のコツ:手間を惜しまずお作法に従う
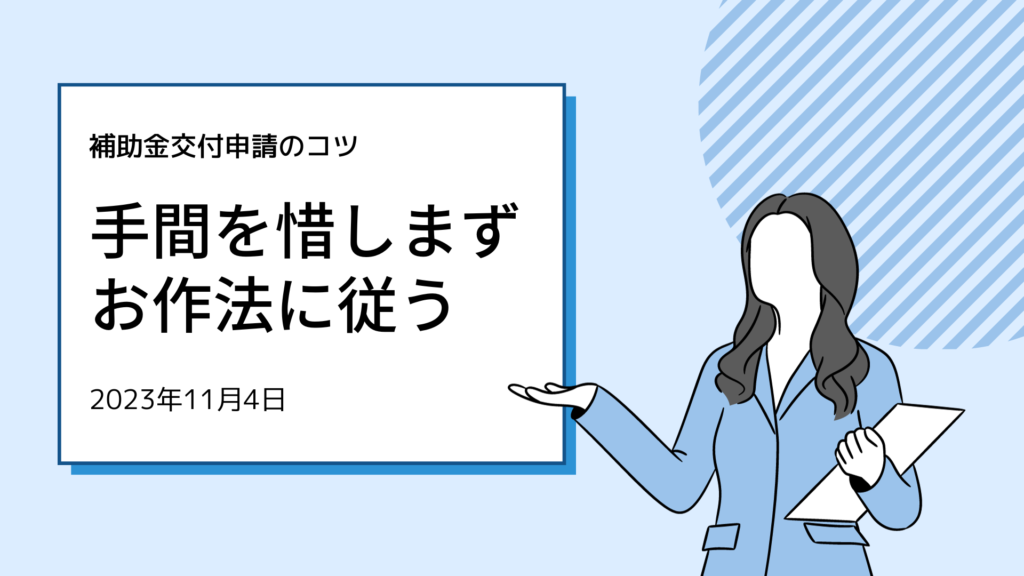
交付申請とは?
補助金の交付申請とは、補助事業を始めるための経費に関する確認を行い補助金交付決定額を決める大事な作業です。
補助金の交付申請は、事業を開始するための資金援助を受ける重要なステップです。
多くの事業者にとって、このプロセスは困難で面倒に感じられるかもしれませんが、実は、適切な準備と理解があれば、案外スムーズに進むことも可能です。
もくじ
交付申請の現実
事業計画が採択されるのも容易ではありませんが、
事業計画は申請サポートを依頼すれば、事業者は事業に関する思いを熱く2~3時間語れば、申請サポート業者がある程度、その思いをまとめてくれて、あなたは修正を指示するだけで、完成へと比較的スムーズに進むと思います。
対して交付申請の実際の申請過程は事業者の負担が大きく、申請サポート側でできることには限界があります。
ここでは、事業者が知っておくべき申請のコツと必要な作業を詳しく解説します。
事業計画書と交付申請の違い
事業計画書は、事業者と申請サポートの共同作業で完成させることができますが、交付申請においては事業者が主導する必要があります。もちろん自分の事業なんですから、あたりまえなんですが、補助金営業と申請サポートが分かれている場合、営業担当が「補助金入金まで丸投げで大丈夫です」と言って営業していたりするので、実際の作業になって、「やること一杯あるなぁ、お金払ってるんだから、やってよ」と思っても、申請サポートでは集められない帳票類がほとんどです。丸投げの姿勢は交付申請時に問題を引き起こすことが多々あります。
お作法に従うことの重要性
補助金申請においては、補助金の「お作法に従う」ことが最も重要です。これは見積書と相見積書の収集から始まり、項目を揃え、見積書に含まれるべきではない「諸経費」「管理費」「現場管理費」等の項目を避けることを含みます。
通常の商習慣として、見積と相見積を取れば、機械を一台入れるだけ、と言うような見積でない限り、細部まで項目が一緒になることなんてまず無いと思います。ですが、補助金事務局は項目の一致を求めます。しょうが無いんです、求めるんですから従うしかありません。
商習慣だと言って項目も違う見積と相見積を提出すれば、それだけ交付決定が伸びるだけです。つまり事業の着手も遅れ、入金もさらに先になります。
また「諸経費」「管理費」「現場管理費」等、こちらの良くある項目も事務局は認めてくれません。
これも商習慣で、全体経費の15%とかで乗っかってることが多いですが、公募要領にもダメだと書いてあります。
この場合の対応方法は
簡単な順に
- 内訳が少ないのであれば、見積書自体に手書きで良いので追記
- 内訳が多いのであれば、別紙をexcel、word等で作成
- 諸経費、現場管理費と言う項目の無い見積書の再発行を依頼 です。
最初からこの項目を無くした方が早いです。
見積もりの収集と検証
見積書と相見積書の収集は申請過程の初期段階であり、この段階での正確さが交付申請のスムーズな進行に直結します。
当たり前ですが、見積もりの有効期間にも注意が必要であり、事務局の対応を待つ間に期限が切れてしまわないようにすることが求められます。
補助金によっては、交付申請を提出して、一回で交付決定まで進むことはまれであり、ほぼ修正差戻が行われます。
また、その修正指示が来るまでも提出後数週間かかるなんてこともあります。
提出、修正を繰り返して、交付決定がでるまで半年なんてこともありえます。当然その間事業を始めることも出来ず、また事業実施期間は締切がありますので、そちらも残り時間が少なくなってタイトになります。
注文書と受注書の作成
商習慣ではないかもしれませんが、注文書や受注書は補助金申請において必要不可欠です。これらの文書は、取引の正式な証となり、補助金の交付決定に大きな影響を与えます。
こちらも、注文書はテンプレートがあり、自社で発行するものなので、後からでもすぐに作成できますが
受注書(契約書・請負書)は取引先に発行して頂いたり、テンプレート使っても、わざわざ押印してもらったりと手間がかかります。
(法律上は受注書としてはハンコなくても有効らしいですが)
まとめ
補助金申請の過程は複雑であり、事業者自らが多くの作業を行う必要があります。しかし、これらの手間を惜しまず、補助金のお作法に従うことで、補助金をスムーズに獲得することが可能です。
最終的には、これらの手順を丁寧に実行することが、補助金入金への早道となります。